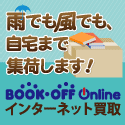予防接種とは
防御システムである免疫の力を利用し、感染防止・発症時の症状の軽減をはかることができます。
予防接種はその感染症の免疫をもたない人に対し、あらかじめ免疫をつくるもとである『ワクチン』を接種し、体の中に抗体をつくり免疫力をつけることです。
免疫とは
さまざまなウイルスや細菌が存在し、それらが体の中に入り感染するといろいろな症状が現れます。 ウイルスや細菌に感染すると、それぞれのウイルスや細菌に対して抗体がつくられます。 この抗体が十分につくられると、次に同じウイルスや細菌が体の中に侵入して来ても発症を防ぐことができます。
この体の防御システムを免疫と言います。
赤ちゃんの免疫はいつ切れるの?
ママのお腹の中でママからもらった免疫や母乳の免疫効果によって守られているのですが、生後半年を過ぎる頃からそれらの免疫が切れ始め、感染の危険にさらされることになります。
また、ママ自身が感染したことのないウイルスや細菌に対しては赤ちゃんもそれらに関しては免疫がありません。
接種の時期は
母体からの移行抗体の減衰や感染症の発生状況、感染症の重症度などを考慮し、接種時期が決められています。
ワクチンの種類
【生ワクチン】
細菌やウイルスの病原体でるウイルスや細菌が持っている毒性を弱め生きた状態で接種します。
生きた状態で接種しますから、その病気に軽く罹った状態になり、免疫をつけます。
生ワクチンには、BCGワクチン・ポリオワクチン・麻疹ワクチン・おたふくかぜワクチン・風疹ワクチン・水痘ワクチンがあります。
【不活化ワクチン】
細菌やウイルスを殺したり、それらの毒素がはたらかないようにして、病原体中から免疫ができるのに必要なものだけを取り出してつくられたものです。
体の中で増えることがないため、抗体をつくらせるには複数回の接種が必要となります。
不活化ワクチンには、百日せきワクチン・日本脳炎ワクチン・インフルエンザワクチン・A型肝炎ワクチン・B型肝炎ワクチン・コレラワクチン・狂犬病ワクチン・DPT三種混合ワクチンなどがあります。
【トキソイド】
細菌の出す毒素を無毒化したもので、不活化ワクチンと同じく複数回の接種が必要です。
トキソイドワクチンには、ジフテリアワクチン・破傷風ワクチンなどがあります。
予防接種の種類
【勧奨接種(定期接種】
感染すると重症化したり、感染力が強い感染症の予防のために、国や自治体が「受けるように努力する義務がある」と強くすすめている予防接種です。
勧奨接種には、BCGワクチン・ポリオワクチン・DPT三種混合ワクチン・DT二種混合ワクチン・MR(麻疹ワクチン・風疹ワクチン)・日本脳炎ワクチン・インフルエンザワクチンなどがあります。
【任意接種】
接種するかどうかの判断は個人の事情や考えで決める予防接種です。
任意接種には、おたふくかぜワクチン・水痘ワクチン・A型肝炎ワクチン・B型肝炎ワクチン・コレラワクチン・狂犬病ワクチンなどがあります。
接種方法の種類
【集団接種】
日程をその地域の自治体が決め、一つの会場に集まって接種する方法。
ポリオ・BCG
※自治体によって異なることがあります。
【個別接種】
個別で小児科に行き接種してもらう方法。
日頃、診察を受けているかかりつけの小児科医によって、接種が行われるため安心できる。
MR・三種混合・おたふくかぜ・水痘・インフルエン
接種方法の時期
三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)
1回目
生後3か月〜7歳6か月未満
(3〜8週間隔(20日以上おいて56日以内の間隔)で3回接種)
1期追加
生後3か月〜7歳6か月未満
(1期初回終了後6か月以上の間隔をおいて1回接種)
2期
11〜13歳未満(1回接種)
※ジフテリア・破傷風トキソイドを接種
麻しん風しん予防接種
1期
1歳〜2歳未満
(麻しん風しん混合ワクチンを1回接種)
2期
小学校就学1年前から就学前日(3月31日)までの期間(いわゆる幼稚園・保育園年長クラスの幼児)
(麻しん風しん混合ワクチンを1回接種)
3期
中学1年生
(麻しん風しん混合ワクチンを1回接種)
4期
高校3年生相当
(麻しん風しん混合ワクチンを1回接種)
日本脳炎
1期初回
生後6か月〜7歳6か月未満
(1〜4週間隔(6日以上おいて28日以内の間隔)で2回接種)
1期追加
生後6か月〜7歳6か月未満
(1期初回終了後おおむね1年以上間隔をおいて1回接種)
2期
9歳から13歳未満
ポリオ麻痺
生後3か月〜7歳6か月未満(6週間(41日)以上の間隔で2回接種)
BCG接種(結核)
生後6か月未満
まぁくんの店のアカウントをフォローする
予防接種(リスト)

.jpg)